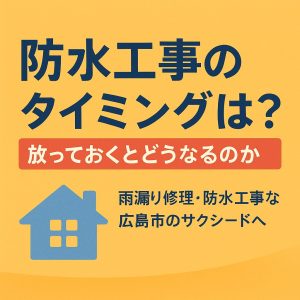外壁と屋上、どっちが雨漏りの原因?広島でよくあるケースと対策方法
「雨漏り=屋根」だと思っていませんか?
雨漏りと聞くと、多くの方が「屋根(屋上)からの浸水」を想像します。
しかし実際の現場では、「外壁」から雨水が浸入しているケースも少なくありません。
この記事では、広島市で防水工事を行っている「防水のサクシード」が、屋上・外壁それぞれの雨漏り原因とその見分け方、対策方法をわかりやすくご紹介します。
屋上からの雨漏り|主な原因と症状
■ ウレタンやFRP防水層の劣化
屋上の床面には防水層が施工されていますが、紫外線や熱の影響で徐々に劣化していきます。
10年以上メンテナンスしていない場合は、ひび割れや膨れが発生して雨漏りの原因になります。
■ 排水口(ドレン)の詰まり
落ち葉や土埃などで排水が詰まると、水が溜まりやすくなり、わずかな隙間から雨水が浸入するリスクが高まります。
■ 施工不良
以前の防水工事の仕上がりに問題があると、数年で雨漏りが再発することも。
外壁からの雨漏り|主な原因と症状
■ シーリング(コーキング)の劣化
外壁の目地や窓周りのゴム状のシーリング材は、年数が経つと硬化・ひび割れを起こします。
ここから雨水が入り込むと、壁内を伝って天井や床に染みを作ることがあります。
■ 外壁のクラック(ひび割れ)
モルタルやサイディング外壁にできた0.3mm以上のクラックは、雨水の侵入口になり得ます。
■ バルコニーと外壁の取り合い部分
建物の構造上、バルコニー周辺は雨水がたまりやすく、接合部の防水処理が甘いと漏水します。
実際の現場では「複合原因」が多い
実際に広島で対応している現場では、「屋上と外壁どちらも原因だった」というケースが多々あります。
雨水は建物の高いところから低いところへ流れていくため、見えている染みと実際の浸入口が一致しないこともあります。
雨漏りの正確な特定には「散水試験」や「赤外線診断」
防水のサクシードでは、目視点検に加え、必要に応じて散水試験・赤外線サーモグラフィを用いて浸水箇所を特定します。
一時的な補修ではなく、根本からの解決を重視しています。
まとめ|外壁も屋上も、10年を目安に点検を
雨漏りの原因は屋上・外壁どちらにも潜んでいます。
特に築10年以上経過している建物は、防水層やシーリングの劣化が進んでいる可能性が高いため、定期点検がおすすめです。
「染みが出た」「天井がポタポタする」など、少しでも異常を感じたら、早めのご相談が建物の寿命を守ります。